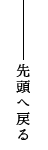月別アーカイブ: 2025年5月
つつみ百貨店のトピック~盆提灯~
こんにちは、つつみ百貨店、更新担当の中西です。
さて今回は
つつみ百貨店のトピック~盆提灯~
ということで、盆提灯の歴史・意味・文化的背景・現代での意義について深くご紹介いたします。

お盆の夜、静かに揺れる盆提灯の光。それは、ただの飾りではなく、長い年月を経て受け継がれてきた“日本人の心の表現”です。
🕰️ 盆提灯の歴史・平安時代から続く迎え火の文化
盆提灯の原型は、平安時代にまで遡るとされています。お盆の起源は仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」という行事で、地獄で苦しむ亡者を供養するための法要がその始まりです。
これが日本古来の祖霊信仰と結びつき、“ご先祖さまが年に一度、あの世から帰ってくる”という考えが定着。迎え火と送り火によって霊を導き、もてなす風習が生まれました。
江戸時代になると、提灯の製造技術が発達し、「迎え火・送り火」の象徴として盆提灯が用いられるようになりました。明治以降は家庭での仏事が一般化し、盆提灯が先祖供養の必需品となっていきます。
🙏 盆提灯に込められた意味
盆提灯には、ただ灯りをともす以上の精神的な意味合いが込められています。
-
霊を迎える道しるべとして
-
冥界からの一時的な帰還を温かく迎える証として
-
ご先祖への感謝の心を“形”として表すものとして
その光は、現世とあの世をつなぐ“架け橋”であり、今を生きる私たちの「敬い」の象徴です。
また、盆提灯を贈るという行為は、「あなたの大切な方の霊を丁寧にお迎えしてください」という気遣いでもあります。
🌸 現代における盆提灯の在り方
現代の住環境やライフスタイルの変化により、盆提灯の形も多様化しています。
-
コンパクトなLED型:省スペースで安全、マンション住まいの方に人気
-
モダン仏壇に合う洋風提灯:現代的な意匠ながらも伝統を受け継ぐデザイン
-
家紋や名前入りの特注提灯:格式を重んじるご家庭向けの本格派
特に、新盆(初盆)を迎えるご家庭では、特別な意味を持つ盆提灯の準備が重要視され、親族や知人からの贈答用としても選ばれます。
🧧 贈り物としての盆提灯──思いやりを形に
盆提灯は仏事の贈答品としても高く評価されており、形式だけでなく気持ちを丁寧に伝える手段として活用されています。
-
新盆を迎える親族へのご挨拶に
-
ご家族を亡くされた方への慰めと励ましに
-
仏事の返礼や供養のお供えとして
贈答用盆提灯には、熨斗(のし)・名入れ・包装などもご用意しており、仏事のマナーに配慮した対応が可能です。
✨ “心を灯す”日本の美しい風習
盆提灯は、単なる仏具ではなく、ご先祖と今を生きる私たちを結ぶ大切な灯りです。
その優しい光は、家族の絆、命の尊さ、感謝の心を静かに伝えてくれます。
時代が変わっても、変わらぬ想いを灯し続ける盆提灯。
一つひとつの灯りに、ご家族の“祈り”を込めてみてはいかがでしょうか。
仏事や盆提灯の選び方についてのご相談は、
こちらから承っております。
お気軽にお問い合わせください。
つつみ百貨店のトピック~盛かご~
こんにちは、つつみ百貨店、更新担当の中西です。
さて今回は
つつみ百貨店のトピック~盛かご~
ということで、盛かごの起源からその意味、現代でのあり方までを深くご紹介します。


日本の仏事や法要において、「盛かご(もりかご)」は、供物を美しく整えて飾る重要な文化的要素のひとつです。故人への敬意や感謝、遺族への配慮を表現する手段として、今なお多くの場で用いられています。
1. 盛かごとは?
盛かごとは、果物や乾物、缶詰、お菓子などを竹かごや台に盛りつけた供物の一種で、通夜・葬儀・法要の際に故人に供えるためのものです。特に地方によっては「供花」と並んで必須の供物として扱われる地域もあります。
2. 盛かごの歴史的背景
■ 起源と古代の供物文化
-
日本の供養文化は仏教伝来以前から存在しており、穀物や果物を神仏に捧げる風習がありました。
-
仏教が伝来して以降、「食べ物を通じて功徳を積む」思想と結びつき、供物が形式化・美化されていきました。
-
特に江戸時代には、見た目の美しさや格式が重視され、竹細工や精巧な盛りつけが行われるように。
3. 盛かごの意味と役割
① 故人への供養と感謝
-
故人が生前に好んだ品や、季節の果物を供えることで、思い出を分かち合う
-
「あの世でも豊かに過ごしてほしい」という願いを込める
② 遺族への配慮と支援
-
香典とは別に、「形として残る供え物」として渡す
-
法要後には参列者への返礼や分配として活用される
③ 地域性・格式の表現
-
盛かごの内容や大きさには、地域ごとの伝統や宗派の影響が色濃く反映される
-
「〇〇家からの供え物」として、個人・団体の気持ちを表す形式
4. 盛かごの種類と内容
主な構成品
-
果物類:りんご、バナナ、みかんなど
-
乾物類:昆布、椎茸、鰹節など
-
缶詰・加工品:ジュース、缶フルーツ、菓子など
-
日用品系(近年増加傾向):洗剤、油、ラップなど
地域差の一例
-
東北・北海道:乾物中心、和紙での装飾が丁寧
-
関西・中部:果物盛り合わせの需要が高い
-
九州:盛かご自体を高く積み上げる「段かご」様式が多い
5. 現代における盛かごの変化
-
簡略化傾向:核家族化・高齢化により、小型化・持ち帰り重視の傾向あり
-
カタログ供物の登場:選べる返礼品として供物をデジタルで表現
-
エコ意識:プラスチック包装を減らし、再利用可能なカゴや紙素材を使用するケースも増加
6. 盛かごを選ぶ際のマナーと注意点
-
宗教・宗派によって避けるべき品目(肉・酒など)があるため、事前確認を
-
仏式・神式・キリスト教式では意味合いや作法が異なるため、TPOを意識
-
表書きや名札をつけて、贈り主が明確にわかるように
盛かごは、単なる供物ではなく、祈り・敬意・絆の象徴です。
目に見える形で想いを伝える日本人ならではの心遣いとして、今も多くの場面で大切にされています。
その一つひとつに込められた気持ちを汲み取りながら、故人と向き合う時間を丁寧に過ごしたいものです。
つつみ百貨店のトピック~竹灯~
こんにちは、つつみ百貨店、更新担当の中西です。
さて今回は
つつみ百貨店のトピック~竹灯~
ということで、今回は竹灯の歴史的背景やその意味、現代の活用例について詳しく解説します。


大分県国東市。豊かな自然と歴史、仏教文化の香りが漂うこの地で、静かに受け継がれてきた伝統工芸があります。それが「薫竹灯籠(くんちくとうろう)」です。
夜の静けさの中に浮かび上がる竹灯籠の柔らかな光──それは、ただの照明ではありません。竹そのものが放つ温もりと香り、そして職人の手仕事による美しさが織り成す、心に響く一灯です。
🛠️ 薫竹灯籠の製造過程──自然と向き合う静かな時間
薫竹灯籠が生まれるまでには、長い時間と繊細な技術が必要です。
まず、工房の近くにある竹林から、一本一本厳選した竹を切り出します。ただ切るだけではなく、自然の力を受けた最良の状態の竹を見極める目が問われます。
その竹はすぐに加工せず、一定期間、静かに寝かせて乾燥させます。竹に含まれる油分を抜くため、専用の窯で二度焼入れを行い、丁寧に燻していきます。
この工程では、温度調整が極めて重要。職人は、わずかな熱の変化にも神経を尖らせながら、十日以上の時間をかけてじっくりと仕上げていきます。
こうして完成した燻竹は、自然な光沢と香ばしい香りを宿し、**まるで生き物のような“生命力”**を感じさせる一本になります。
仕上げに行う「掘り」の工程では、独自に開発された治具を使い、一つ一つの模様を繊細に彫り上げていきます。その全てが手仕事であり、二つとして同じものはありません。
🎁 世界に一つだけの灯籠──贈り物としての薫竹
薫竹灯籠の魅力は、見た目の美しさや製法だけにとどまりません。完全オーダーメイドでの制作にも対応しており、お客様の想いを形にすることができます。
-
家紋を彫り込んだ慶事・仏事の灯籠
-
お誕生日や還暦・米寿など長寿のお祝いに、祝絵入りの灯籠
-
記念品や感謝の贈り物として、唯一無二の竹灯籠
手に取った瞬間、その香りと輝きから「特別な品」であることが伝わる薫竹灯籠。大切な方への贈り物として、あるいはご自身の心を癒す“ひと灯”として、幅広い場面でご利用いただけます。
✨ 伝統と未来を結ぶ“灯り”
薫竹灯籠は、国東の自然と文化、そして人の手と心が織り成す芸術です。その一灯に込められた温かさは、見る人の心を静かに照らし、忘れがたい記憶として残ります。
この美しい伝統が、次世代へ、そして世界へと受け継がれていくことを願いながら──
つつみ百貨店のトピック~切子灯籠~
こんにちは、つつみ百貨店、更新担当の中西です。
さて今回は
つつみ百貨店のトピック~切子灯籠~
ということで、今回は大分県に伝わる深い歴史と文化的背景、そして切子灯籠ならではの特徴についてご紹介します。


大分県臼杵市に伝わる「切子灯籠(きりことうろう)」は、華麗で優美な姿と、仏教文化に根ざした精神性を併せ持つ伝統的な盆提灯です。その発祥は江戸時代にさかのぼり、京都文化の影響を受けながら臼杵の地で独自に発展してきました。
〜 京都から臼杵への文化継承 〜
切子灯籠のルーツは、江戸時代の臼杵藩主・稲葉家が参勤交代で京都に赴いた際に、都の洗練された工芸文化を臼杵へ持ち帰ったことに始まるとされています。特に、仏教儀礼の中で使われる提灯文化が臼杵の地で独自の形に進化し、現在の切子灯籠へと昇華されました。
臼杵は中世から仏教文化が深く根付いていた土地で、国宝に指定された「臼杵石仏」などが象徴的です。このような精神風土が、切子灯籠の美と宗教的意味を形作る大きな土壌となったのです。
切子灯籠の特徴 〜 造形美と回転する灯の幻想 〜
切子灯籠の最大の魅力は、その精緻で繊細な造形です。主な特徴は以下の通りです:
-
多面体構造:12面体の火袋(ひぶくろ)には、切り込み模様が施され、外光を繊細に透過します。
-
回り灯籠:内部に組み込まれた風車が電球の熱で回転し、光と影がゆっくりと動く幻想的な効果を生み出します。
-
絹の袴(はかま):灯籠の下部には絹の布が垂らされ、まるで風にたなびくような優雅な動きを演出します。
-
金箔の香立て:中心には金色の装飾が置かれ、光を反射して煌めく様はまさに極楽浄土の表象とも言えるでしょう。
このような意匠は、単なる照明器具としてではなく、亡き人をしのぶ「心の象徴」として人々に親しまれています。
行事と文化継承 〜 切子灯籠の生きる場面 〜
切子灯籠は、主にお盆の時期や仏教法要で使用され、家々の仏壇や寺院に飾られます。特に臼杵市では以下のような行事でその姿を見ることができます
-
国宝臼杵石仏火まつり(8月):篝火や灯籠が灯され、石仏を幻想的に照らします。
-
うすき竹宵(11月):臼杵城下町を竹ぼんぼりと切子灯籠が美しく彩る、秋の風物詩です。
これらの行事では、地域の人々が協力し、切子灯籠を手作りするワークショップも行われ、伝統の継承が図られています。
〜 時を超えて灯る祈りのかたち 〜
切子灯籠は、単なる工芸品ではなく、臼杵の歴史、信仰、文化が凝縮された象徴です。京都から受け継がれた美意識と、臼杵の宗教的土壌の中で熟成されたその姿は、今も人々の心に深い安らぎと祈りの時間をもたらしています。
その柔らかな光の奥にある、数百年にわたる人々の想いと美の系譜に、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。