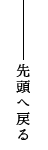日別アーカイブ: 2025年5月1日
つつみ百貨店のトピック~切子灯籠~
こんにちは、つつみ百貨店、更新担当の中西です。
さて今回は
つつみ百貨店のトピック~切子灯籠~
ということで、今回は大分県に伝わる深い歴史と文化的背景、そして切子灯籠ならではの特徴についてご紹介します。


大分県臼杵市に伝わる「切子灯籠(きりことうろう)」は、華麗で優美な姿と、仏教文化に根ざした精神性を併せ持つ伝統的な盆提灯です。その発祥は江戸時代にさかのぼり、京都文化の影響を受けながら臼杵の地で独自に発展してきました。
〜 京都から臼杵への文化継承 〜
切子灯籠のルーツは、江戸時代の臼杵藩主・稲葉家が参勤交代で京都に赴いた際に、都の洗練された工芸文化を臼杵へ持ち帰ったことに始まるとされています。特に、仏教儀礼の中で使われる提灯文化が臼杵の地で独自の形に進化し、現在の切子灯籠へと昇華されました。
臼杵は中世から仏教文化が深く根付いていた土地で、国宝に指定された「臼杵石仏」などが象徴的です。このような精神風土が、切子灯籠の美と宗教的意味を形作る大きな土壌となったのです。
切子灯籠の特徴 〜 造形美と回転する灯の幻想 〜
切子灯籠の最大の魅力は、その精緻で繊細な造形です。主な特徴は以下の通りです:
-
多面体構造:12面体の火袋(ひぶくろ)には、切り込み模様が施され、外光を繊細に透過します。
-
回り灯籠:内部に組み込まれた風車が電球の熱で回転し、光と影がゆっくりと動く幻想的な効果を生み出します。
-
絹の袴(はかま):灯籠の下部には絹の布が垂らされ、まるで風にたなびくような優雅な動きを演出します。
-
金箔の香立て:中心には金色の装飾が置かれ、光を反射して煌めく様はまさに極楽浄土の表象とも言えるでしょう。
このような意匠は、単なる照明器具としてではなく、亡き人をしのぶ「心の象徴」として人々に親しまれています。
行事と文化継承 〜 切子灯籠の生きる場面 〜
切子灯籠は、主にお盆の時期や仏教法要で使用され、家々の仏壇や寺院に飾られます。特に臼杵市では以下のような行事でその姿を見ることができます
-
国宝臼杵石仏火まつり(8月):篝火や灯籠が灯され、石仏を幻想的に照らします。
-
うすき竹宵(11月):臼杵城下町を竹ぼんぼりと切子灯籠が美しく彩る、秋の風物詩です。
これらの行事では、地域の人々が協力し、切子灯籠を手作りするワークショップも行われ、伝統の継承が図られています。
〜 時を超えて灯る祈りのかたち 〜
切子灯籠は、単なる工芸品ではなく、臼杵の歴史、信仰、文化が凝縮された象徴です。京都から受け継がれた美意識と、臼杵の宗教的土壌の中で熟成されたその姿は、今も人々の心に深い安らぎと祈りの時間をもたらしています。
その柔らかな光の奥にある、数百年にわたる人々の想いと美の系譜に、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。